
「収入がない専業主婦(主夫)でも、老後の備えってできるのかな?」「iDeCoって働いている人向けじゃないの?」そのように思っている人もいるでしょう。
実は専業主婦もiDeCoに加入でき、将来の年金対策としても非常に有効な制度です。
本記事では、iDeCoの制度概要から、専業主婦がiDeCoを利用するメリット・デメリット、NISA制度との違いや使い分け方をわかりやすく解説します。
目次

専業主婦でも条件を満たせばiDeCoに加入することができます。 ここでは、iDeCoの基本的な仕組みと、専業主婦の加入条件と掛金の上限、2025年以降に予定されている制度の改正ポイントを解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が掛金を拠出し、自ら運用し、60歳以降に受け取る私的年金制度です。主な特徴は以下の通りです。
このような仕組みによって、中長期的な資産形成を支援する制度となっています。
専業主婦は国民年金における「第3号被保険者」に該当します。これは、会社員や公務員である配偶者の扶養に入っており、本人に厚生年金や国民年金の支払い義務がない人を指します。
iDeCoではこの第3号被保険者も加入対象に含まれており、20歳以上60歳未満であれば専業主婦でも加入可能です。
掛金の上限は、第3号被保険者の場合、月額2万3,000円(年額27万6,000円)と定められています。
ただし、収入がまったくない場合は所得控除による節税メリットはありません。あくまでも「自分名義の老後資産を形成する手段」として考えるのが現実的です。

iDeCoにはさまざまなメリットがあります。専業主婦に限った話ではありませんが、iDeCoの利点を知り、どのような恩恵があるのかを理解しておきましょう。
通常、投資信託・預金などで得た利息や売却益には、約20.315%(所得税+住民税等)が税金として差し引かれます。
しかし、iDeCoは、運用益に税金がかからず再投資できるという制度優遇があります。
長期で積み立て運用するほど、この「税金を払わずに複利で運用できる」効果は大きくなります。
拠出した掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税・住民税の負担が軽くなります。
ただし、専業主婦の場合はそもそも課税所得がないことが多いため、所得控除のメリットは他の加入者と比べて限定的になります。少額でもパートなどで扶養の範囲を超える給与所得がある方にとっては、節税効果も得られるでしょう。
60歳以降に受け取る際、一括で受け取る「一時金方式」なら「退職所得控除」、分割で受け取る「年金方式」なら「公的年金等控除」が適用され、一定額までは課税されない枠があります。
自分の状況に合わせて受取方式を選べる点もメリットです。
専業主婦は、自身の公的年金(国民年金の第3号被保険者分)以外の年金がないため、iDeCoを活用して「自分名義の老後資金を準備できる」という安心感があります。配偶者の収入に依存せず、自分で積み立てた資産があるということは、精神的な自立にも貢献します。
今後ライフスタイルが変わりパートや就業を始めた場合でも、iDeCoは継続可能です。加入区分が変わっても運用資産はそのまま引き継がれ、掛金の上限も変更できるため、柔軟に対応できます。

収入が少ない専業主婦の場合、流動性やコストに注意が必要です。以下では、主な注意点と、それをどう回避・対処できるかまで含めて詳しく解説します。
iDeCo の最大の制約の一つは、原則として積み立てた資金を 60 歳になるまでは引き出せないことです。
しかも、加入期間が10年未満の場合は、60歳時点で給付を受け取る資格がなく、受給開始が後ろ倒しになる可能性もあります。
iDeCo にはさまざまな手数料・コストがかかります。これらが長期運用の足枷になることがあります。
特に、掛金が少ない期間が長くなるほど、コストが運用リターンを食いつぶしてしまう可能性があります。手数料が利益を上回る「マイナス運用」になるケースも起こりうる点には要注意です。
iDeCo では、自分で運用商品を選択する必要がありますが、選んだ商品や運用結果によっては元本割れする可能性があります。特にリスク資産(株式・株式型投信など)を多く選ぶと、価格変動の影響を大きく受けやすくなります。
iDeCoの節税メリットである「所得控除」は、加入者に課税所得があることが前提です。専業主婦で扶養の範囲内で働いている場合、この控除の恩恵はありません。
つまり、「節税を期待して始めたが、実際には税金がもとから低いためメリットが薄かった」というケースがありえます。
子どもの教育費、住宅購入、介護費、医療費など、大きな支出が見込まれるライフステージでは、流動性の低いiDeCoに資金を固定しすぎてしまうと資金繰りが苦しくなる可能性があります。
また、掛金が引き落とせない月が出てしまった場合でも、その月も口座管理手数料は発生するため、運用資産が目減りすることがあります。
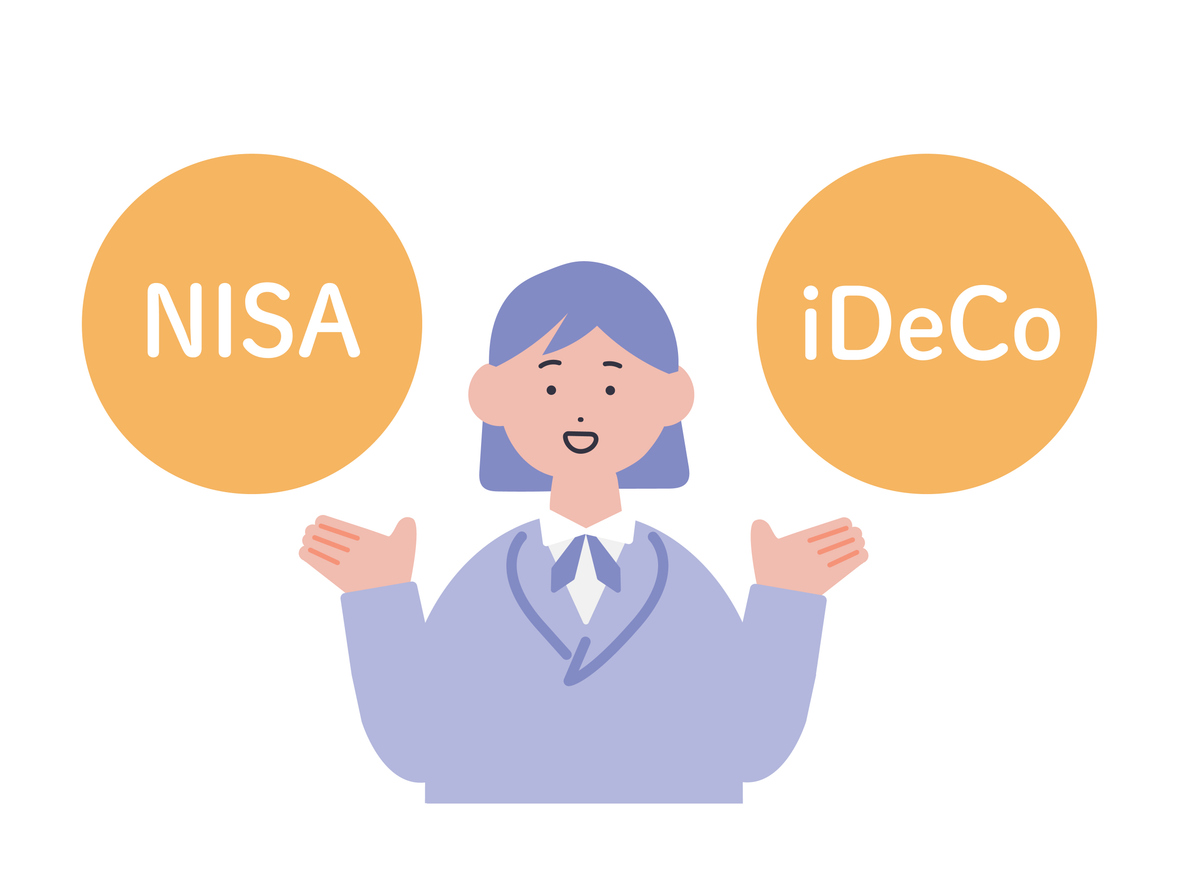
資産形成手段としては、iDeCoだけでなくNISAも選択肢になります。専業主婦の方が資産形成を考える際、制度の違いを理解しておくことが重要です。
iDeCoとNISAはさまざまな違いがありますが、主に以下の違いがあります。
NISAはいつでも売却・引き出し可能ですが、iDeCo は原則として60歳まで引き出せない制度です。また、NISAもiDeCoも運用益は非課税ですが、NISAは掛金拠出時・受取時の所得控除はありません。
掛金の上限については、NISAは職業などによる違いがなく年間360万円まで投資ができます。一方で、iDeCoは専業主婦(第3号被保険者)だと掛金上限は年間27万6,000円です。また、NISAは100円、1,000円といった少額から投資可能なのに比べ、iDeCoは最低でも月額5,000円の拠出が必要です。
つまり、NISAは自由度が高く流動性を重視した運用に向き、iDeCoは確実に貯められる「老後資金」を前提にした長期運用に向いています。
なお、NISAとiDeCoは併用可能で、それぞれの制度を目的に応じて使い分けるのもいいでしょう。
資産形成を考える際には、自分の目的に応じてiDeCoとNISAを適切に使い分けることが重要です。どちらの制度にも強みがあるため、目的や資金の性質に合わせて選ぶことで、効率的な資産運用が実現します。
| 目的 | 推奨制度 | 備考 |
|---|---|---|
| 税制メリットを活用しながら老後資金を準備したい | iDeCo | 税制優遇が手厚く、掛金拠出時に控除がある点が強み |
| 流動性重視・教育資金・住宅資金 | NISA | 引き出し自由・資金流用しやすい |
| 長期運用+資産形成 | NISAとiDeCoを併用 | NISAで中期余裕資金を運用しつつ、iDeCoで老後備えも確保 |
将来の年金不安に備えたい方は、iDeCoを優先的に活用するのが効果的です。iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となるうえ、運用益も非課税、さらに受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。税制優遇が三段階で得られることが大きな魅力です。
資金を途中で引き出す可能性がある場合は、NISAを活用することを推奨します。NISAは非課税で運用できるうえ、引き出しの制限がないため、教育費や住宅資金など中長期的な支出にも対応しやすい柔軟な制度です。
中期的な資産形成と老後資金の両立を目指す方には、NISAとiDeCoの併用が適しています。NISAで中期的に使う可能性のある余裕資金を運用し、iDeCoで老後に備えることで、目的別の資金管理と効率的な運用が両立できます。
このように、資産形成の目的に応じて制度を選ぶことが、将来に向けた安定的なマネープランを築くための第一歩となります。

最後によくある質問を紹介します。
iDeCoの手続きの流れは以下のとおりです。
通常、運用開始まで1~2カ月程度かかることを見込んでおきましょう。
七十七銀行のiDeCoは以下からご確認いただけます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
毎月の拠出額や年利にもよりますが、長期で積み立てるほど複利効果が大きくなることが特徴です。以下にシミュレーションをしてみましょう。
| 積立期間 | 積立総額 (元本) |
運用益 | 最終積立額 (元本+運用益) |
|---|---|---|---|
| 20年 | 240万円 | 約170万円 | 約410万円 |
| 30年 | 360万円 | 約470万円 | 約830万円 |
このように、月1万円という少額でも、年利5%で運用した場合、20年間で約410万円、30年間では約830万円に達します。積立総額に対して、運用益だけで数百万円が上乗せされる計算です。
長期運用を前提とするiDeCoでは、少額からでも早く始めることが資産形成の成功に直結します。途中で引き出せないという制約も、老後資金として確実に残すという観点では大きなメリットとなります。

iDeCoは、将来の年金不安が広がる今の時代において、自分自身で老後資金を準備できる非常に有効な制度です。専業主婦という立場でも加入できる点、運用益が非課税になる点、そして長期で積み立てることで資産形成につながる点など、多くの魅力があります。
一方で、60歳まで引き出せないという流動性の制限や、手数料、運用リスク、節税効果が限定的な場合があることなど、注意すべきポイントも確かに存在します。しかし、これらのリスクは事前に理解し、対処法を講じることで、十分に乗り越えることができます。
iDeCoを始めるかどうか迷っている方は、まずは資料請求や金融機関の比較などから始めてみてください。状況によっては流動性の高いNISAから検討したり、iDeCoと併用することで、より柔軟で効果的な資産形成を目指すこともできます。資産形成は、ライフスタイルや家計状況に合わせて検討しましょう。
【七十七銀行 関連ページ】
※この記事は2025年9月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。