
副業を始めると、「税金はどうなる?」「いくら稼いだら申告が必要?」「節税できる方法はある?」といった疑問が出てくるものです。結論から言うと、副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
さらに、「所得」は収入から経費を引いた額であるため、副業にかかった必要経費を差し引くことで非課税ラインに収まる可能性もあります。条件によっては非課税に近い状態を保ったり、節税によって税負担を抑えたりすることも可能です。
本記事では、副業の税金に関する基礎知識から、非課税になる条件、合法的な節税対策までを初心者にもわかりやすく解説します。
目次

副業を始めて収入を得ると、その所得に対して税金を納める義務が発生します。会社員の場合、本業の給与からは税金が天引きされていますが、副業で得た所得については自分で計算し、申告・納税する必要があります。まずは、副業に関連する税金の基本を理解しましょう。
副業で得た所得には、主に「所得税」と「住民税」がかかります。
所得税は、個人の所得に対してかかる国税です。所得が多くなるほど税率が上がる「累進課税」が採用されています。副業で一定以上の所得を得た場合、確定申告を行い納税します。
住民税は、お住まいの都道府県や市区町村に納める地方税です。所得税の確定申告を行えば、その情報が自治体に共有されるため、別途住民税の申告をする必要は基本的にありません。
また、副業が事業的規模で行われていると判断された場合、個人の事業税が課されるケースもあります。
税金を計算する上で、「収入」と「所得」の違いを正しく理解することが重要です。
収入とは、副業で得た売上そのものを指します。例えば、ライター業で10万円の報酬を得た場合、この10万円が収入です。
一方、所得とは、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた後の金額を指します。計算式で表すと「収入 − 必要経費 = 所得」となります。
税金は収入ではなく、この所得に対して課税されます。
副業で得た所得は、その内容によって主に3つの区分に分けられます。
一つ目は、アルバイトやパートのように雇用契約に基づいて収入を得る「給与所得」です。本業の勤務先以外から給与を受け取っている場合に該当します。
二つ目は、継続的・安定的に収益を上げており、独立して事業として行っている場合の「事業所得」です。Webデザインやライター、コンサルティングなどを個人で請け負うケースが考えられます。
三つ目は、上記のいずれにも当てはまらない場合の「雑所得」です。単発の講演料やフリマアプリでの売上など、一時的な収入がこれに分類されることが多く、多くの会社員の副業が該当します。
どの所得区分に該当するかによって、確定申告の方法や節税の選択肢が変わるため、ご自身の副業がどれに当たるか確認しておくことが大切です。

「副業を始めたら、必ず確定申告が必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、所得税に関しては、必ずしも全員が確定申告をしなければならないわけではありません。
ここでは、その基準となる「20万円ルール」と、非課税の条件について解説します。
会社員(給与を1か所から受けている人)の場合、副業で得た年間の所得が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。これは「20万円ルール」として知られています。
ただし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う場合は、20万円以下の副業所得も合わせて申告する必要があるため注意が必要です。
副業の収入が20万円を超えていても、収入から必要経費を差し引いた「所得」を20万円以下に抑えることで、所得税の確定申告が不要になる可能性があります。
例えば、年間の副業収入が30万円あったとします。このままでは確定申告が必要ですが、もし副業に関連する経費が11万円あった場合、所得は19万円(30万円 - 11万円)となります。結果として、所得税の確定申告は不要となります。
どのようなものが経費として認められるかを正しく理解し、漏れなく計上することが、賢い副業の税金対策の第一歩です。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることを忘れてはいけません。住民税には「20万円ルール」のような非課税の規定がなく、所得が発生した場合は原則としてお住まいの自治体に申告する義務があります。
確定申告をすれば、そのデータが自治体にも連携されるため個別の住民税申告は不要です。しかし、20万円以下で確定申告をしない場合は、自分で市区町村の役所へ住民税の申告手続きを行わなければなりません。申告を怠ると、後から追徴課税される可能性もあるため、必ず手続きを行いましょう。
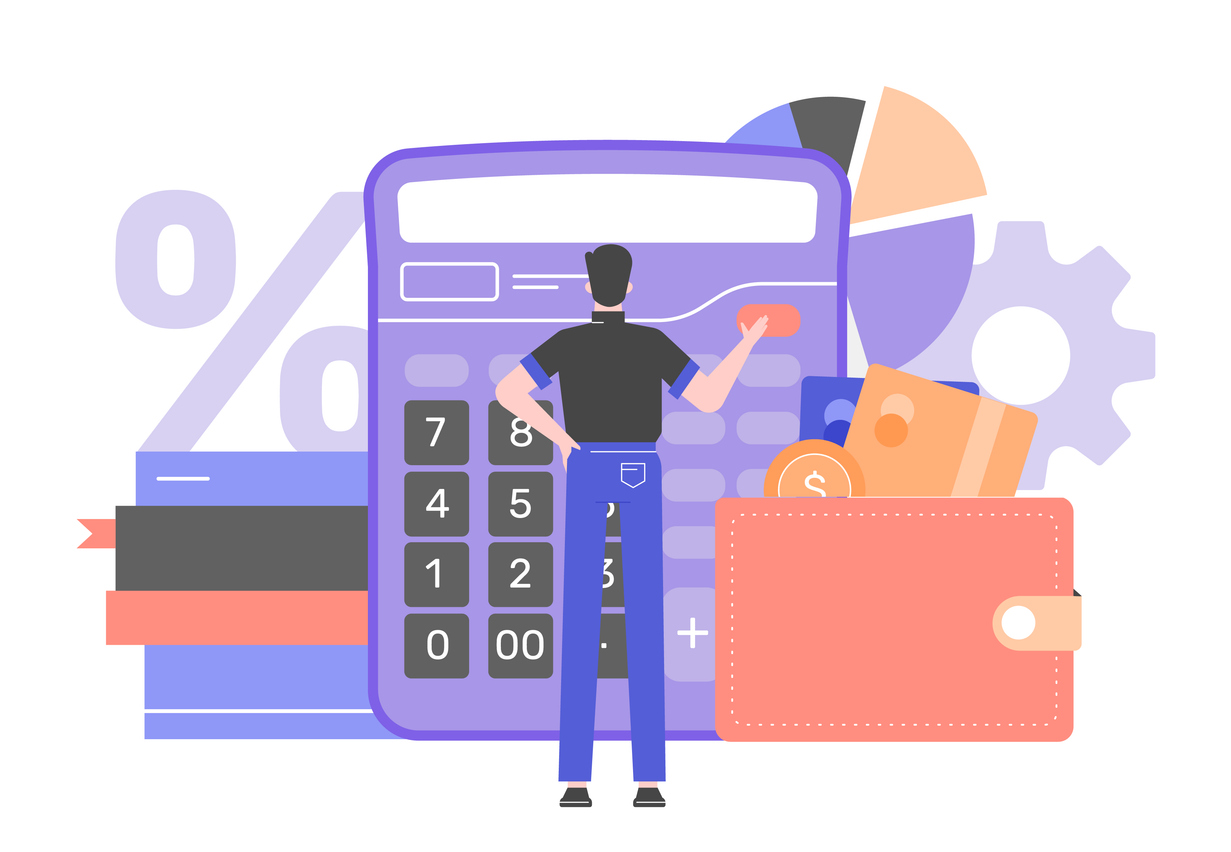
副業で得た利益を最大限手元に残すためには、適切な副業の節税対策が欠かせません。ここでは、誰でも実践できる合法的な税負担の軽減方法を具体的に紹介します。
最も基本的かつ効果的な節税策は、必要経費を正確に計上することです。副業の収入を得るために直接かかった費用は、経費として収入から差し引くことができます。
例えば、Webライターであれば、パソコンの購入費用やインターネットの通信費、参考文献の購入費などが経費になります。
自宅で仕事をしている場合は、家賃や電気代の一部を仕事で使った割合に応じて経費とする「家事按分」も可能です。領収書やレシートは必ず保管し、何が経費になるのかを正しく把握して漏れなく計上しましょう。
確定申告をする際、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。白色申告は手続きが簡単で帳簿も簡易ですが、特別控除はありません。
一方で「青色申告」を選択することで大きな節税メリットを受けられます。事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、複式簿記で記帳すると最大65万円の控除が受けられるほか、赤字の繰越しや家族への給与支払いの控除など多くのメリットがあります。
所得が65万円減ることで、所得税と住民税を大幅に抑えることが可能です。
副業を事業所得として青色申告を行いたい場合は、まず税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
開業届は、事業を開始した日から1か月以内に提出することが定められています。青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、事業開始日から2か月以内)に提出する必要があります。これらの書類を提出することで、青色申告の恩恵を受けられるようになります。
ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)、生命保険料控除といった各種控除制度の活用も有効な節税策です。これらの制度は、本業の所得と副業の所得を合算した総所得金額から控除されます。
総所得金額が減ることで、課税対象となる金額が少なくなり、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。会社員として年末調整で各種控除を申請している方も、確定申告をすることで、副業所得を含めた全体の所得に対して改めて控除を適用できるため、節税に繋がります。
iDeCoについては以下の記事で詳しく解説しています。
iDeCoはデメリットしかないという誤解を解消!制度内容とメリットを解説
iDeCoとNISAはどっちを優先する?違い・使い分け・年代別の選び方を解説

実際に税金の申告を行う際の手順と、必要な書類について解説します。計画的に準備を進めることで、申告期限間近に慌てることを避けられます。
なお、確定申告の期限は原則として毎年3月15日(休日の場合は翌平日)です。この日までに申告書の提出と、税金の納付を完了させる必要があります。還付申告であれば翌年1月1日から5年間提出可能ですが、納税が発生する場合は必ず期限内に行うことが重要です。期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があります。準備は1月中に始めると安心です。
すでに解説したように、副業の所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
白色申告は記帳のルールが緩やかで、比較的手軽に行えます。一方で、青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、複式簿記での記帳や決算書の作成が必要になりますが、最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字の繰越や家族への給与の経費計上など、多くの節税メリットがあります。副業の規模や継続性に応じて選びましょう。
確定申告では、副業の収入を証明する書類(報酬明細、請求書、振込記録など)や、必要経費の領収書・レシートが必要です。経費には、自宅の一部を仕事用に使った場合の家賃・光熱費の按分や、通信費、備品代なども含まれます。また、本業がある場合は源泉徴収票の添付も必要です。加えて、マイナンバーや本人確認書類の提出も求められるため、余裕をもって準備しましょう。
申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でオンライン作成が可能です。質問形式で入力するだけで、税額計算や必要書類の出力まで自動で行われます。紙で提出する場合は、印刷して押印・添付書類を準備します。青色申告の場合は、青色申告決算書の作成も必要となるため、会計ソフトの利用が便利です。クラウド会計サービスを活用すると、帳簿作成と申告書作成がスムーズに行えます。
申告書の提出は主に以下3つの方法から選べます。
近年はe-Taxが推奨されており、還付のスピードも早く便利です。スマートフォンでもマイナンバーカード方式でe-Taxが可能になっており、紙提出よりも手続きが簡素化されています。初めての人も利用しやすくなっています。また、青色申告はe-Taxを選択することで控除額が55万円から65万円になります。
確定申告の結果、所得税の納付が必要な場合は、3月15日までに納税を行います。納付方法には、銀行振込、クレジットカード、コンビニ払い、ダイレクト納付(e-Tax)などがあります。
反対に、税金を納めすぎていた場合は還付金を受け取ることができ、申告から通常3週間〜1カ月程度で指定口座に振り込まれます。どちらの場合も、申告内容と納付・還付状況を控えとして保存しておくことが大切です。

節税はルールに則って行うことが大前提です。誤った方法や過度な節税は、かえってペナルティを課されるリスクを伴います。注意すべき点を理解しておきましょう。
節税の基本は経費の計上ですが、事業と無関係なプライベートな支出を経費にしたり、金額を水増しして申告したりすることは脱税行為にあたります。税務署の調査で不審な点が見つかった場合、申告が否認され、本来納めるべき税金に加えて、延滞税や過少申告加算税といった追徴課税が発生する恐れがあります。
また、毎年赤字を計上し続けていると、事業としての実態が疑われ、そもそも事業所得ではなく趣味の範囲と見なされる可能性もあります。経費はあくまで「事業に関連するもの」という原則を忘れないようにしましょう。
所得が大きくなると、個人事業主よりも法人を設立した方が税率上有利になる場合があります。いわゆる「法人化」も節税の一つの選択肢です。
しかし、法人を設立すると、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割(最低でも年間7万円程度)が発生します。さらに、社会保険への加入が義務付けられ、税理士への報酬など、個人事業主の時にはなかったコストや手間が増加します。節税メリットだけでなく、これらのデメリットも総合的に考慮し、慎重に判断することが重要です。

副業の税金手続きをスムーズに進め、効果的な節税を実現するためには、日頃からの準備と意識が大切です。成功のための2つのポイントを紹介します。
確定申告の時期になってから1年分の領収書や売上をまとめるのは、非常に大変な作業です。日頃から会計ソフトなどを活用し、取引が発生するたびに記録する習慣をつけましょう。
こまめに帳簿付けを行うことで、経費の計上漏れを防げるだけでなく、自身の副業の経営状況をリアルタイムで把握することにも繋がります。これにより、適切な事業判断や新たな節税対策の検討も可能になります。
「自分のこの支出は経費になるのか?」「どの所得区分で申告すれば良いのか?」など、税金に関する判断は複雑で迷うことも少なくありません。そのような時は、一人で悩まずに専門家へ相談することをおすすめします。
税務署の無料相談窓口を利用したり、税理士に相談したりすることで、正確で最適なアドバイスを得られます。特に、副業の規模が大きくなってきた場合や、節税方法についてより詳しく知りたい場合は、税理士への相談が有効な手段となるでしょう。

最後に、副業の税金に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
まず、副業を始める前に、必ず勤務先の就業規則を確認しましょう。会社によって副業の扱いは異なり、「原則禁止」「許可制」「届出制」などさまざまです。「服務規律」や「遵守事項」といった項目に記載されていることが多いので、内容をよく読んでください。
もし就業規則で副業が明確に禁止されているにもかかわらず無断で行うと、規則違反として懲戒処分の対象となる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、会社のルールに従うことが鉄則です。許可や届け出が必要な場合は、必ず正規の手続きを踏みましょう。
副業が赤字になった場合、申告するメリットがあるかどうかは所得区分によって異なります。
副業が「事業所得」または「不動産所得」に分類され、赤字が出た場合は、確定申告をすることで本業の給与所得と損益通算ができます。損益通算とは、副業の赤字を本業の給与所得など他の黒字の所得と合算することを指します。
例えば、給与所得が500万円、副業の事業所得が50万円の赤字だった場合、これらを相殺して総所得を450万円にすることができます。総所得が減るため、納めるべき税額も少なくなり、すでに天引きされている所得税の一部が還付される可能性があるため、赤字でも申告した方が有利です。
一方で、副業が「雑所得」に分類される場合、赤字が出ても他の所得と損益通算することはできません。したがって、税金面でのメリットはないため、申告の必要はありません。

副業における税金の知識は、安心して収入を増やしていくために不可欠です。まず基本として、副業の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は原則として不要ですが、その場合でも住民税の申告は別途必要になる点を忘れないようにしましょう。
また、収入から必要経費をしっかりと差し引くことで、所得を20万円以下に抑え、結果的に副業を非課税にできる可能性もあります。さらに、事業所得として青色申告を行ったり、各種控除制度を賢く利用したりすれば、合法的な副業の節税を進めることも可能です。
副業を始めたばかりの方にとって、税金の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、正しい知識を身につけて計画的に準備を進めれば、難しいことはありません。本記事を参考に、適切な税金対策を行い、健全な副業ライフを送りましょう。
※この記事は2025年8月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。