
「亡くなった人が遺言書を遺していても、遺留分は侵害できない」という話を聞いたことはありませんか?
遺留分とは、一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。たとえば、父親が遺言書で第三者に財産を渡すよう指定すれば、遺された配偶者や子どもたちの生活が立ち行かなくなる可能性があります。そこで、民法では配偶者や子どもに最低限の遺産相続を求める権利を認めています。これが遺留分制度です。
本記事では、遺留分と法定相続分との違いや遺留分の割合、万が一遺留分が侵害されたときの対処法を詳しく解説します。
目次

遺留分とは、一定範囲の相続人に対して保証されている、最低限の相続財産留保分を指します。被相続人の死後、遺された相続人の生活を保障するために、民法では一定範囲の相続人に対し、遺留分を求める権利を定めているのです。
たとえば、「相続人ではない愛人に全財産渡す」「相続対象の子どもは4人いるが、1人の子どもだけに全財産相続させる」といった遺言の場合、遺された相続人の生活が困窮する可能性もあります。
遺留分制度は、「遺言の自由をある程度制限して、遺された相続人の生活を守るもの」と考えるとわかりやすいでしょう。遺族の生活を守るという意味合いがあるため、兄弟姉妹には遺留分の権利はない点に注意が必要です。
2019年に民法が改正され、相続に関するルールが変わりました。遺留分制度も改正の対象となり、2019年7月1日以降に生じた相続から改正内容が適用されています。
主な改正のポイントは、相続人が遺留分権利を請求する際に「物的権利」ではなく「金銭」を請求できるようになったことです。
たとえば、遺留分を請求する相手が被相続人の愛人で対象の財産がマンションだとします。この場合、遺留分を請求する相続人(子どもや配偶者)は、愛人とマンションの持ち分を共有しなければなりません。
法改正前は物的権利の請求により、複雑な共有状態が発生することもあったのです。法改正後は侵害された遺留分の支払いを金銭で求められるようになったため、マンションなどの物的財産を共有するという複雑な状態を避けられるようになりました。

相続人には、あらかじめ取り分として定められている「法定相続分」があります。では法定相続分と遺留分は何が違うのでしょうか。違うポイントは以下のとおりです。
法定相続分は、民法で定められている、相続財産(遺産)を相続する割合を指します。ただし、遺言書や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる遺産割合に変更することは可能です。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められている、最低限の相続財産(遺産)の割合を指します。遺言書で指定されている相続分が少なく、遺留分に満たない場合は、自身の遺留分を請求できます。
法定相続分は、遺言がない場合に相続財産を分けるための目安であり、強制力はありません。
遺留分は、相続財産を最低限もらえる権利です。ただし、権利があってもそれを行使するかどうかは相続人の自由です。自身の遺留分を侵害されていても、権利を行使しなければ相続内容は変わりません。
相続人は自動的に遺留分をもらえるわけではないため、遺言内容に不満がある場合は遺留分請求の訴えを起こす必要があります。

上述したとおり、遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人です。相続人の範囲と遺留分の割合について、詳しく見ていきましょう。
原則として、遺留分を請求できるのは兄弟姉妹(甥姪)以外の相続人です。
具体的には、以下の相続人が遺留分請求の権利を持っています。
遺留分は、亡くなった人(被相続人)に養われていた人の生活を保障するための制度であるため、兄弟姉妹は対象外となることを覚えておきましょう。
遺留分は「法定相続割合の2分の1または3分の1」と定められていて、その割合は相続の順番によって変わります。
| 相続人 | 遺留分 | 法定相続分 | 各相続人の具体的な遺留分割合 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみが相続人 | 相続財産の2分の1 | 相続財産全て | 配偶者 2分の1 |
| 子のみが相続人 | 相続財産の2分の1 | 相続財産全て | 子ども 2分の1 |
| 子+配偶者が相続人 | 相続財産の2分の1 |
配偶者 2分の1 子ども 2分の1 |
配偶者 4分の1 子ども 4分の1 |
|
配偶者+父母または 祖父母が相続人 |
相続財産の2分の1 |
配偶者 3分の2 父母・祖父母 3分の1 |
配偶者 3分の1 父母・祖父母 6分の1 |
| 父母または祖父母が相続人 | 相続財産の3分の1 | 相続財産全て | 直系尊属 3分の1 |
上記の割合を元に、具体的な遺留分の計算例を見ていきましょう。
ここでは被相続人が夫で相続財産は5,000万円とし、夫が亡くなった場合の遺留分・法定相続分を遺族のパターンごとに計算しました。
法定相続分は5,000万円ですが、遺留分は全体の相続財産に対して2分の1になるため合計2,500万円となります。それぞれの割合は以下のとおりです。
法定相続分は5,000万円ですが、遺留分は全体の相続財産に対して2分の1になるため合計2,500万円となります。それぞれの割合は以下のとおりです。
法定相続分は5,000万円ですが、遺留分は全体の相続財産に対して2分の1になるため合計2,500万円となります。子どもが複数人いるときは、遺留分・法定相続分ともに人数で分割します。そのため、それぞれの割合は以下のとおり同じ金額です。

遺留分の請求権を持つ相続人(遺留分権利者)でも、場合によっては遺留分が認められないことがあります。本来の権利者であっても、以下の人は遺留分を主張できません。
相続人が被相続人を殺害したり、遺言書の既存や隠蔽工作などの犯罪行為をしたりすると、相続人の資格を失います。相続人の資格を失った相続欠格者には、遺留分も認められません。
相続人に著しい非行があった、被相続人を虐待していたなどの重大な原因がある場合、被相続人は相続人の地位を奪う手続き(相続廃除)を行うことができます。相続排除された人には、法定相続分も遺留分も認められません。なお、相続の廃除を申し立てできるのは、被相続人だけです。
自らの意思で相続を放棄すると、放棄した人は始めから相続人ではなかったと見なされます。当然、法定相続分も遺留分も認められません。
遺留分の権利を持っていても、家庭裁判所から認可を受ければ遺留分の権利を放棄できます。遺留分を放棄した人には、遺留分は認められません。

たとえば、自身には遺留分として2,000万円の遺産相続権利があるのに、遺言書には相続人以外の人に遺産を全額渡すと書かれていたとします。
このように自身の遺留分がないことを「遺留分の侵害」と呼び、不満がある場合は遺留分侵害額の請求が可能です。ここでは遺留分を侵害されたときの流れや注意点について、詳しく見ていきましょう。
遺留分権利者である相続人には、遺留分を請求できる権利があるため、遺言による相続内容に不満があれば遺留分を求める訴えを起こせます。
ただし、遺留分は自動的に取り分けられるものではありません。不満を持つ相続人が遺留分を求める訴えを起こす必要があります。
訴えを起こす際は、遺留分を求める相手(遺言により遺留分以上の財産を受け取った人)との話し合いから始めます。しかし、話し合いで解決しなければ家庭裁判所で調停を申し立て、それでも話し合いがまとまらなければ裁判をして決着を付けることになります。
裏を返せば、自身の遺留分が侵害されていても不満がなく、故人の意思を尊重する場合には遺留分を請求する必要はありません。
被保険者が生前から支援していた慈善事業の団体に寄付したい、経営していた会社の後継者に遺贈したいといった理由がある場合もあるでしょう。個人の意思を尊重し、遺留分を主張しないという選択も可能です。
遺留分の請求権には、以下2つの「期限」があるため注意しましょう。
遺言の内容に不満があっても、長期間話し合いを放棄してしまうと、あっという間に1年経って時効を迎えてしまいます。少しでも不満があるときは、速やかに遺留分を求める訴えを起こしましょう。
遺留分を請求する際の具体的な流れは、以下のとおりです。
遺留分の請求は揉めることが多いとされています。交渉が長引けば1年の時効を迎えてしまうため、遺留分侵害額請求の訴訟経験が豊富な弁護士を探し、早めに相談しましょう。
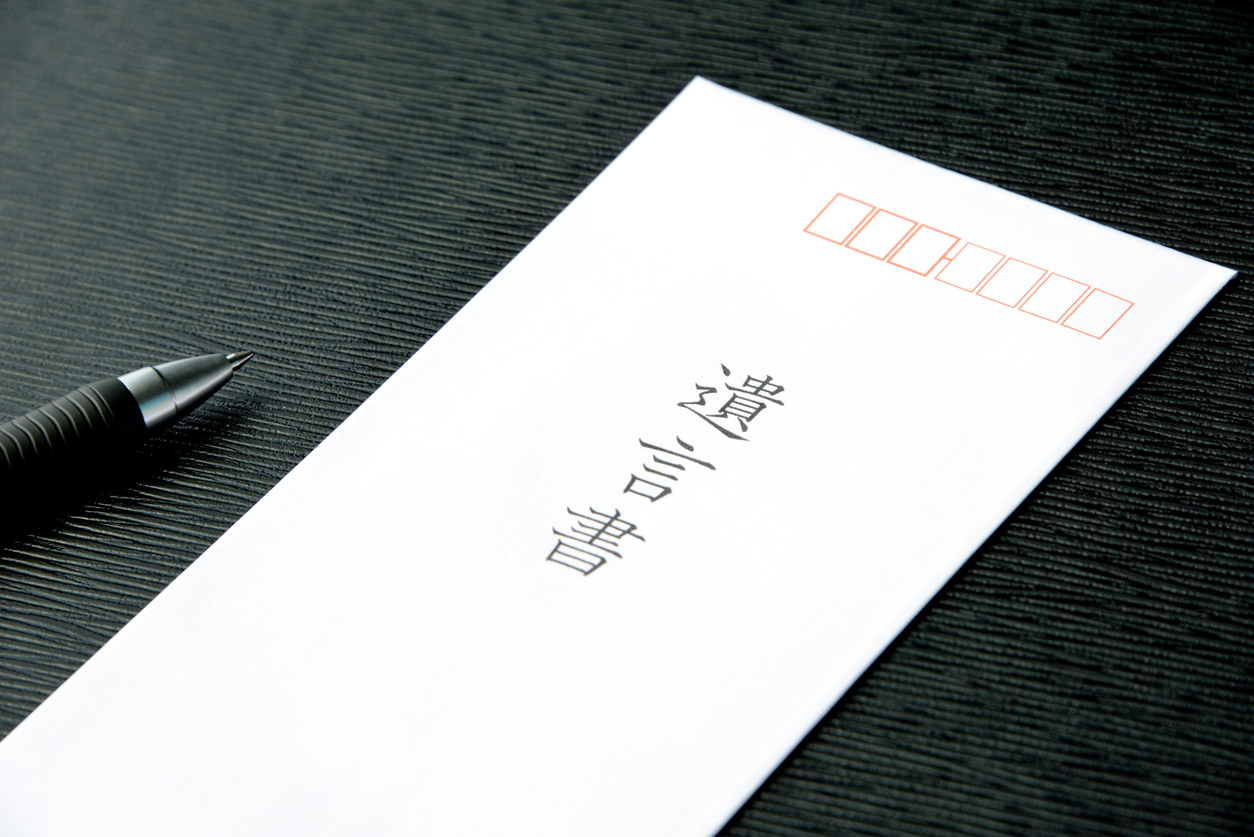
遺留分の問題の多くは、被相続人が遺留分を無視した遺言書を作成してしまうことで発生します。
これから遺言書を作成する人は、遺留分にくれぐれも気をつけたうえで遺言書を作成しましょう。自身の遺言書を作成するとき、あるいは家族が遺言書を作成するときには、相続の専門家に相談し、アドバイスを得ることをおすすめします。
相続について相談できる専門家は、税理士や弁護士などがいます。また、財産管理のプロである金融機関で相談することも可能です。
七十七銀行では、財産を遺す側・受け取る側、それぞれの立場にそった相続のお悩みをサポートしています。遺言書作成の事前相談や実際の作成と保管、遺言の執行などを任せられる「遺言信託」や、複雑な相続手続きをサポート・代行する「遺産整理業務」まで、複数の相続サービスをご用意しています。身近な金融機関の手を借り、家族間の相続トラブルを未然に防ぐのも一つの方法です。相続に関する相談自体は無料なので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
【七十七銀行 関連ページ】
※この記事は2023年1月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。