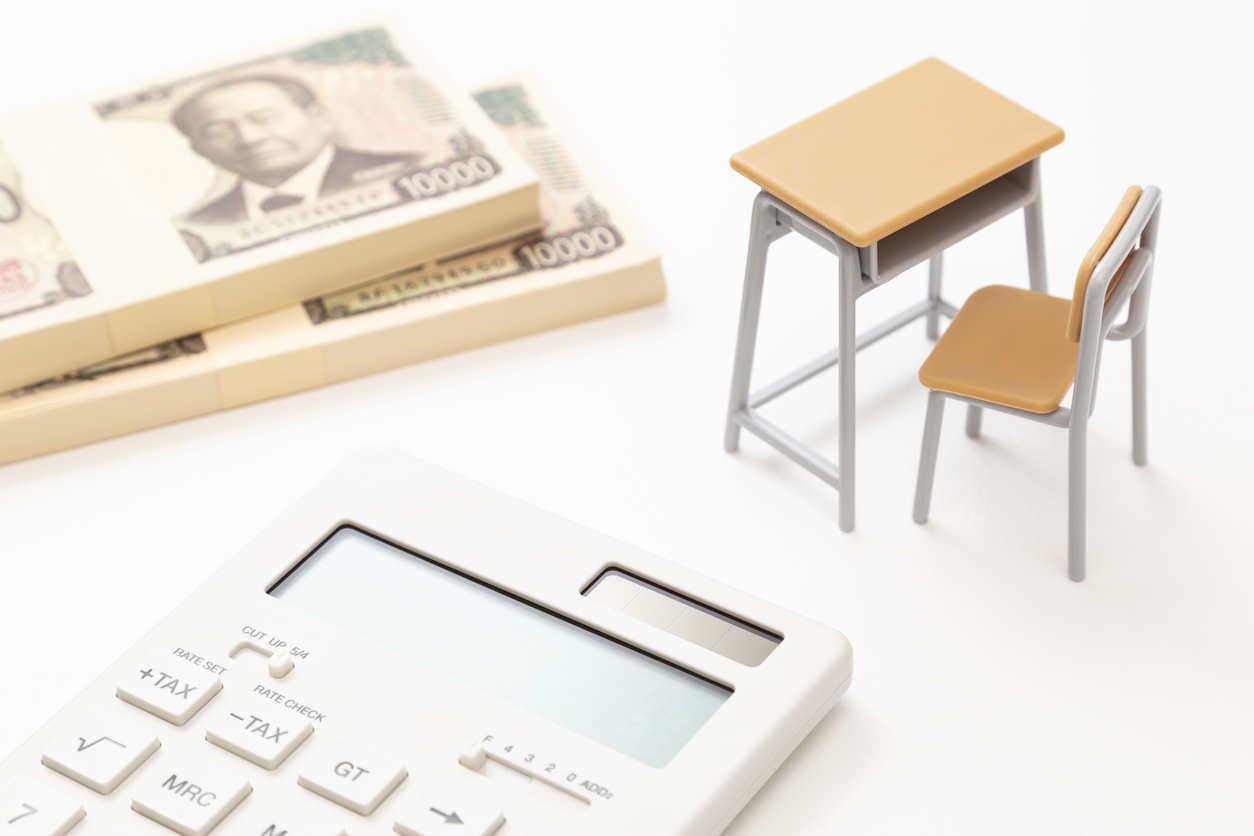
大学の入学金や学費は、進学先や学部によって大きく異なるため、国公立・私立・短大・専門学校などの費用目安を把握し、生活費や通学費も含めて資金計画を立てることが重要です。本記事では、各教育機関の学費の目安と、入学金や学費が払えない場合の具体的な対処法について詳しく紹介します。
目次

進学先の選択肢として、国公立大学や私立大学、短期大学、専門学校などがありますが、進路を決めるうえで学費は大きなポイントです。ここでは、主な進学先の入学金や授業料の目安を紹介します。
ただし、以下に紹介する金額は、あくまでも入学金と学費の目安です。教科書などの学用品費や通学費、さらに親元を離れて進学する場合は引越し費用、生活費、住居費なども考慮する必要がある点に注意しましょう。
国立大学の入学金、授業料は、文部科学省が標準額を定めています。
| 入学料 | 授業料(年額) |
|---|---|
| 28万2,000円 | 53万5,800円 |
授業料は年額なので、4年間で「53万5,800円×4年=214万3,200円」となります。
つまり、入学金(28万2,000円)と4年分の授業料(214万3,200円)を合計すると、国立大学にかかる費用の目安は約243万円です。
ただし、各国立大学は文部省が定める標準額の120%を上限として、入学金・授業料・検定料を設定することができます。そのため、最大で約292万円程度になる可能性も考慮しておきましょう。
また、実際に2025年度入学から、一部の国立大学で授業料を標準額の120%に引き上げる動きも始まっています。
一方、公立大学の学費は国立大学と大きく異なりませんが、大学が指定する地域に住んでいるか、地域外に住んでいるかで入学金が変わる点が特徴です。
下記の金額は、文部科学省のサイトで公表されている公立大学の平均的な授業料と、地域外からの入学者に適用される入学金の金額です。
| 入学料 | 授業料(年額) |
|---|---|
| 37万4,371円 | 53万6,191円 |
出典:私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について:文部科学省 >(参考2)国公私立大学の授業料等の推移
私立大学の学費は、大学ごとに自由に設定されるうえ、学部によっても異なりますが、全体的には国公立大学に比べて高めの傾向にあります。特に、理科系学部や医歯系学部の学費は、他の学部よりも高額になる傾向が見られます。
| 授業料 | 入学料 | 施設設備費 | |
|---|---|---|---|
| 文科系学部 | 82万7,135円 | 22万3,867円 | 14万3,838円 |
| 理科系学部 | 116万2,738円 | 23万4,756円 | 13万2,956円 |
| 医歯系学部 | 286万3,713円 | 107万7,425円 | 88万566円 |
| その他学部 | 97万7,635円 | 25万1,164円 | 23万1,743円 |
出典:私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について:文部科学省 >(資料1)令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
授業料と施設設備費は年額であり、在学中は毎年支払う必要があります。
学部ごとの在学期間中にかかる学費の目安を算出したものが下表です。なお、医学部や歯学部は卒業までに6年かかるため、ほかの学部に比べて総額が高額になります。
| 在学期間中にかかる費用(※) | 入学料 | 合計(目安) | |
|---|---|---|---|
| 文科系学部 | (82万7,135円+14万3,838円)×4年=388万3,892円 | 22万3,867円 | 410万7,759円 |
| 理科系学部 | (116万2,738円+13万2,956円)×4年=518万2,776円 | 23万4,756円 | 541万7,532円 |
| 医歯系学部 | (286万3,713円+88万566円)×6年=2,246万5,674円 | 107万7,425円 | 2,354万3,099円 |
| その他学部 | (97万7,635円+23万1,743円)×4年=483万7,512円 | 25万1,164円 | 508万8,676円 |
※「授業料+施設設備費」を在学年数分合計した金額
さらに、学科によっては実験実習料やその他費用も発生する場合があり、これらの合計金額の平均は11万2,058円です。
私立大学は学費の設定に幅があるため、実際に進学を検討する際は、各大学・学部の公式情報や要項を確認して、より正確な情報を得ることが大切です。
短期大学も公立よりも私立のほうが高い傾向があります。一方、専門学校は選択する分野や学科、修業年数によって学費が大きく変わり、実習費や設備費が高額になる場合があります。
修業年数や、実習費、施設設備費などを事前に調べておきましょう。
以下に入学金と年間にかかる学費の一例を紹介します。
| 授業料(年額) | 入学料 | |
|---|---|---|
| 公立短期大学 | 37万7,357円 | 22万5,050円 |
|
授業料 (年額) |
入学料 |
施設設備費 (年額) |
実験実習料 (年額) |
その他 (年額) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 私立短期大学 | 72万9,069円 | 23万7,122円 | 16万3,836円 | 4万229円 | 10万1,732円 |
|
授業料 (年額) |
入学金 |
実習費 (年額) |
設備費 (年額) |
その他 (年額) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 専門課程 | 73万6,000円 | 17万8,000円 | 12万1,000円 | 17万円 | 8万1,000円 |
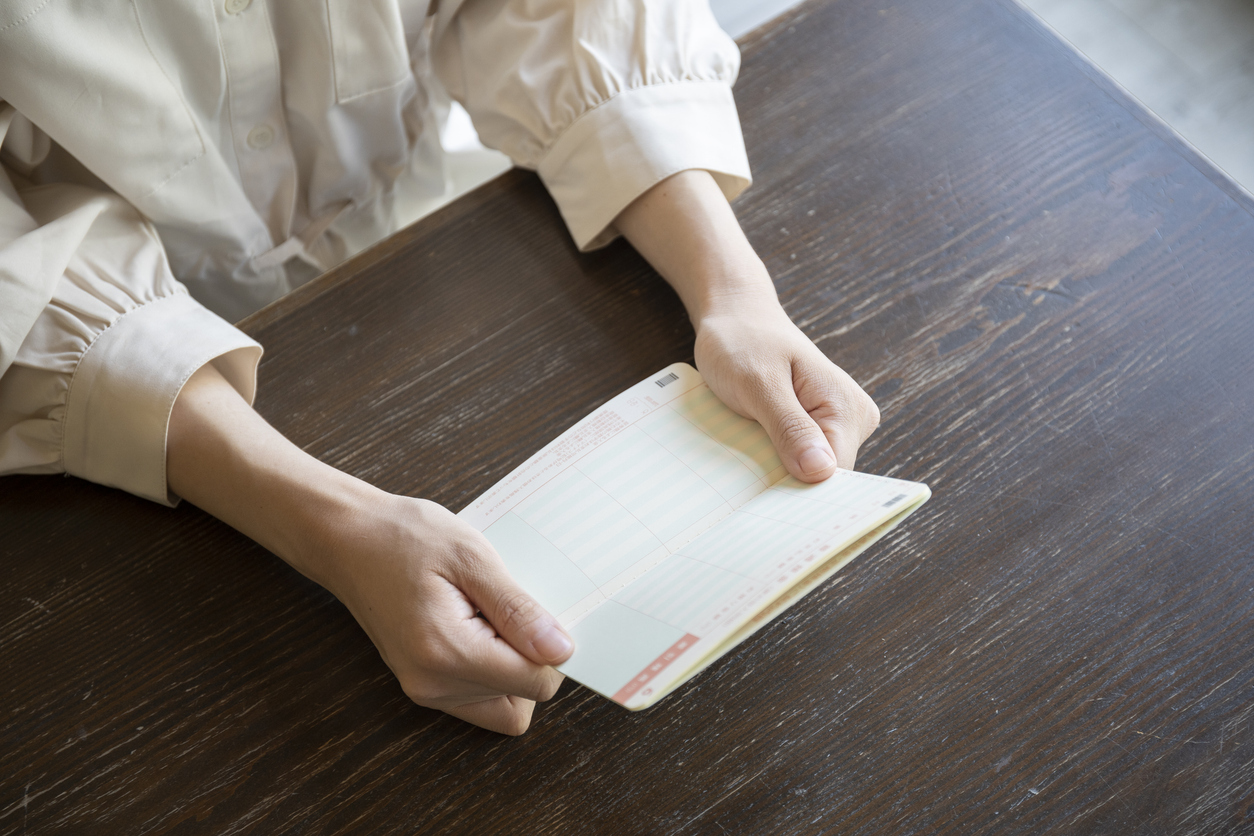
学費の納入には期限が設けられており、これを過ぎると「授業料納入のお願い」などの通知が届きます。記載されている期限内に学費を納めないと、除籍処分になる可能性があります。学費の未納によって除籍になるタイミングは、学校によって異なるため、学則を確認しておきましょう。
学費の滞納が原因で除籍になり、復籍する際は、未納分の学費に加えて復籍料の支払いが必要な場合があります。また、多くの場合、再入学にも期限が設けられており、別途入学金の納付や復籍試験への合格が求められるケースがあるため、注意が必要です。
除籍処分を受けると、学歴にも影響するため、入学金や学費の滞納がないよう十分注意しましょう。

大学の入学金や学費が払えない場合は、大学の延納・分納制度や高等教育の修学支援制度、給付型奨学金の利用を検討しましょう。また、利息はかかりますが、国や民間銀行の教育ローンを利用する方法もあります。
入学金だけであれば、カードローンやクレジットカードのキャッシング枠を活用する選択肢も考えられます。
さらに、祖父母からの支援や自治体などの公的支援制度を利用することも可能です。自分の状況に合った制度を早めに確認し、計画的に活用するよう心がけましょう。
経済的な理由で入学金や学費の支払いが難しい場合は、できるだけ早く、入学予定の大学または在籍している大学の学生課・教務課・経理課など、学費に関する担当部署に相談しましょう。
多くの大学では、納付期限の延長や分納(分割払い)などの制度を設けています。ただし、大学ごとに制度の有無や条件、利用できる分割回数・期間などが異なるため、学則や手続き窓口、必要書類などを確認しておくことが大切です。
文部科学省は、経済的な事情によって大学・短期大学・高等専門学校・専門学校への進学機会を失うことがないよう、「高等教育の修学支援新制度」を実施しています。
この制度では、住民税非課税世帯学生が要件を満たした場合、下表のとおり入学金や授業料が金額が免除・減額されます。
| 区分 | 免除・減額の年額 | ||
|---|---|---|---|
| 授業料 | 入学金※2 | ||
| 大学 | 国公立 | 約54万円 | 約28万円 |
| 私立 | 約70万円 | 約26万円 | |
| 短期大学 | 国公立 | 約39万円 | 約17万円 |
| 私立 | 約62万円 | 約25万円 | |
| 高等専門学校 | 国公立 | 約23万円 | 約8万円 |
| 私立 | 約70万円 | 約13万円 | |
| 専門学校 | 国公立 | 約17万円 | 約7万円 |
| 私立 | 約59万円 | 約16万円 | |
※1 昼間制のケース、夜間制は金額が異なります
※2 入学金は一度のみ支給対象
なお、住民税非課税世帯に準ずる世帯の場合、上記金額の2/3または1/3の支援額となります。
令和7年からは、子供を3人以上同時に扶養している間は、所得制限なく現行制度における満額支援と同額の入学金・授業料の支援が受けられます。
また学校によっては独自の学費免除・減免制度を用意しているケースもあるため、あわせて確認するとよいでしょう。
高等教育の修学支援新制度では、給付型奨学金も利用できます。
給付型奨学金は住民税非課税世帯の該当する場合、原則として毎月、以下の金額が学生の口座に振り込まれます。住民税非課税世帯に準ずる世帯に該当する学生は、満額の2/3または1/3の支援額となります。
給付型奨学金は返済する必要がありませんが、世帯収入や資産の要件を満たしていること、学習意欲があること、高校の履修科目の評定平均値が5段階中3.5以上であることなどが条件です。
| 国公立 | 私立 | |||
|---|---|---|---|---|
| 自宅から通う場合 | 自宅以外から通う場合 | 自宅から通う場合 | 自宅以外から通う場合 | |
| 大学・短期大学・専門学校 |
2万9,200円 (3万3,300円) |
6万6,700円 |
3万8,300円 (4万2,500円) |
7万5,800円 |
| 高等専門学校 |
1万7,500円 (2万5,800円) |
3万4,200円 |
2万6,700円 (3万5,000円) |
4万3,300円 |
※3 昼間制・夜間制共通、カッコ内は生活保護世帯で自宅から通学する人、および児童養護施設等から通学する人
また、日本学生支援機構(JASSO)が運営する第一種奨学金(無利子)や、第二種奨学金(有利子)を利用する方法もあります。
奨学金を利用すれば、経済的な事情があっても学校に通えますが、返済が必要なうえ、学力基準や収入基準を満たしていなければ利用できない場合があります。特に第二種奨学金は利息がかかる点にも注意が必要です。
| 区分 | 自宅から通う場合 | 自宅外から通う場合 | |
|---|---|---|---|
| 大学 | 国公立 | 2万円~ 4万5,000円 |
2万円~ 5万1,000円 |
| 私立 | 2万円~ 5万4,000円 |
2万円~ 6万4,000円 |
|
| 短期大学・専門学校 | 国公立 | 2万円~ 4万5,000円 |
2万円~ 5万1,000円 |
| 私立 | 2万円~ 5万3,000円 |
2万円~ 6万円 |
|
| 高等専門学校 | 国公立 | 1万円~ 4万5,000円 |
1万円~ 5万1,000円 |
| 私立 | 1万円~ 5万3,000円 |
1万円~ 6万円 |
|
※4 給付型奨学金と併せて利用する場合、給付型奨学金の支援区分等に応じて、第一種奨学金の貸与月額が調整されます。
【第二種奨学金の貸与月額※5】
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 大学・短期大学・専門学校 | 2万円~12万円(1万円刻み) |
| 高等専門学校 |
|
※5 私立大学の医・歯学の課程や、薬・獣医学課程、法科大学院の法学を履修する課程は、増額できる場合があります。
また、大学や企業が独自で奨学金制度を用意している場合もあります。日本学生支援機構のサイトから検索が可能なので、活用してみましょう。
国や民間の銀行などが提供する教育ローンを利用する方法もあります。ただし教育ローンは利息が発生するため、利用する前に返済計画を立てましょう。
国の教育ローンは国内外の高校、大学、大学院、専門学校・各種学校が対象です。学校の入学金や授業料の他、受験費用、教科書代、通学費用、在学のための住居費用(敷金・礼金含む)、留学費用、学生の国民年金保険料など、用途が幅広い点が特徴です。
融資限度額は学生・生徒1人につき350万円(用途によっては450万円)、金利は年2.65%の固定金利です。比較的低金利で利用できる反面、世帯年収や扶養している子どもの人数によっては利用できない場合があります。
民間の銀行が扱っている教育ローンは、世帯年収による利用制限がありませんが、変動金利のものが多く、金利上昇局面では、返済期間中に金利が上昇する可能性があります。また利用するためには、申し込んだ金融機関の審査に通過しなければなりません。
【教育ローンの比較】
| 国の教育ローン | 民間の教育ローン | |
|---|---|---|
| 対象となる学校・用途 |
|
|
| 融資限度額 | 1人あたり350万円(用途によっては450万円) | 金融機関によって異なる |
| 金利 | 年2.65%固定金利 | 変動金利が多い |
| 利用制限 | 世帯年収や扶養家族の人数で利用できない場合がある | 世帯年収の上限は基本的になし |
| 申込時の審査 | 日本政策金融公庫の審査 | 各金融機関の審査 |
入学金だけならカードローンやクレジットカードのキャッシング枠の活用も検討してみましょう。
カードローンとは、利用限度額の範囲内であれば何度でも借り入れができる無担保、保証人不要のローンで、主に民間の銀行や消費者金融で扱われています。
いずれの方法も比較的スピーディに借り入れができますが、クレジットカードにキャッシング枠が設定されている場合は、キャッシング枠の範囲内で審査不要のまま借り入れが可能です。
一方、新規でカードローンを申し込む際は、金融機関の審査に通過しなければなりません。また、カードローンやクレジットカードのキャッシング枠は、教育ローンや奨学金と比べて金利が高い傾向があるため、あらかじめ返済計画を立ててから利用するよう心がけてください。
祖父母などから経済的支援を受ける方法や、自治体の公的支援である「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」や「生活福祉資金貸付制度」を利用する方法もあります。
一般的にお金を贈与してもらう場合には贈与税が課されますが、父母や祖父母の直系尊属からの生活費や教育費の贈与であれば、贈与税の対象外です。
ただし親族間のトラブルを避けるため、資金援助の内容や返済の有無について明確にしておきましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、ひとり親家庭の母または父、あるいは寡婦の方で、20歳未満の子どもを扶養している方などを対象にした貸付制度です。
制度の中には「就学支援資金(入学準備のための資金)」や「修学資金(授業料や書籍代、通学など)」があり、資金が低金利あるいは無利息で借りられます。利用を検討する場合は、最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口で相談してください。
また「生活福祉資金貸付制度」の中には、以下の貸し付けも用意されています。窓口は都道府県の社会福祉協議会です。
これらの公的支援制度は一定の要件を満たす必要があるため、事前に窓口に確認して必要書類や申請時期などを早めに確認しておくことが大切です。

国公立か私立、学部や分野によって学費は大きく異なり、国立大学なら約243万円(最大292万円の可能性も)、私立大学はさらに高額になる場合があります。
短大・専門学校も修業年数や学科次第で費用に差があり、納入を怠ると除籍処分や復籍時の追加費用が発生することもあります。
高等教育の修学支援新制度や奨学金、教育ローンをはじめ、自治体の公的貸付や家族からの支援など、多様な方法から自身に合った方法で早めに準備することが大切です。
七十七銀行では入学金や学費準備するためのローンとして、77教育ローン、77教育カードローン、77医大生ローンを用意しています。
77教育ローンは入学金や授業料の他、下宿・アパート入居費用、他金融機関等の教育ローンの借り換えなど幅広い用途に利用できます。また在学期間に応じて最長5年間、元金返済の据え置きくことが可能です。
77教育カードローンは、借入極度額の範囲内であれば、ATMを通じていつでもお借入れ、ご返済ができます。教育資金専用カードローンのため、通常のカードローンよりも低金利で利用できる点が特徴です。
77医大生ローンは医学部・歯学部・薬学部・獣医学部に進学するための学費の特化したローンで、最大3,000万円まで融資を受けられます。高額な費用がかかる学部を志望する場合でも利用可能です。
詳しくは以下で確認できます。
【七十七銀行 関連ページ】
【参考サイト】
出典:私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について:文部科学省
>(参考2)国公私立大学の授業料等の推移
出典:私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について:文部科学省
>(資料1)令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
出典:公立短期大学授業料等について:文部科学省
※この記事は2025年2月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。