
「相続」という言葉を聞いて皆さんは何をイメージされるでしょうか?
遺産相続をめぐってのトラブルや煩雑な相続手続きなど・・・。マイナスのイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、相続トラブルは決して他人事ではなく、相続手続きも避けて通れません。ここでは、実際に「相続」に直面したとき、できるだけスムーズに相続が進むよう知っておきたい基本的な知識について解説します。
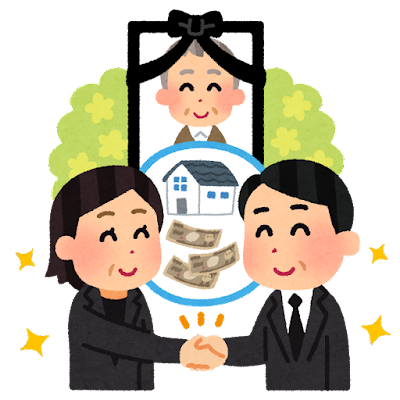
まず「相続」とは、ある人が亡くなったときにその人の財産(すべての権利や義務)を特定の人が引き継ぐことを言います。亡くなった人を「被相続人」、引き継ぐ人を「相続人」と呼びますが、引き継ぐものはすべての権利や義務ですのでプラスの財産(預貯金や家屋・土地など)だけならよいですが、マイナスの財産(借入金など)がある場合、そのどちらをも引き継ぐことになります。
次に、相続人の範囲です。「法定相続人」という言葉がありますが、これは民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことで、遺言書がなければ基本的に法定相続人に相続されます。では、誰が法定相続人になれるかというと、配偶者と血族です。ただ、配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族には優先順位があります。
| 順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 |
死亡した人の子供 その子供が既に死亡している場合は、その子供の直系の卑属(子供や孫など)。 子供も孫もいる場合は、死亡した人により近い子供を優先。 |
| 第2順位 |
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 父母も祖父母もいる場合は、死亡した人により近い父母を優先。 |
| 第3順位 |
死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子供。 |
このとき、第2順位の人は第1順位の人がいない場合に、第3順位の人は第1順位、第2順位の人がいない場合に相続人になります。
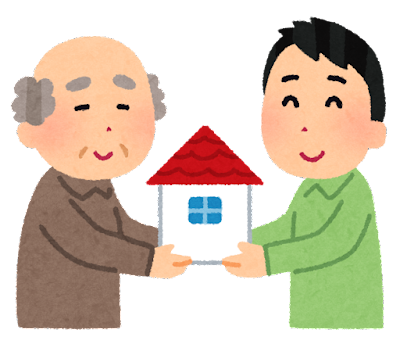
相続にはさまざまな手続きが必要になります。期限も手続きを行う機関もそれぞれ異なり、間に合わなかった場合にはペナルティが科せられる場合もありますので、知っておくと安心です。いざというときにお役立てください。
| 期日 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡診断書の取得/死体埋葬火葬許可証の取得/死亡届の提出 |
| 10日以内 | 年金受給停止の手続き |
| 14日以内 | 国民健康保険証の返却/介護保険の資格喪失届/住民票の除票 |
| なるべく早く | 健康保険証の返却/遺言書の調査・検認/相続人の確定/故人の財産調査/遺産分割協議書の作成/不動産の名義変更登記 |
| 3カ月以内 | 相続放棄または限定承認/相続の承認または放棄の期間の伸長 |
| 4カ月以内 | 故人の所得税の準確定申告 |
| 10カ月以内 | 相続税の申告 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求/高額医療費の請求/生命保険金の請求 |
| 5年以内 | 遺族年金の受給申請 |
このほかにも市役所や区役所のほか、年金事務所、税務署などの手続きも必要です。
手続きが多く期限もあるため、大切な人を亡くしたご家族にとって、相続はかなり大きな負担となります。金融機関や専門家のサービスを利用するなどの検討をおすすします。

相続トラブルはだれにでも起こりうることです。富裕層だけの問題ではなく、いわゆる“中流家庭”にも相続トラブルが多く発生しています。遺産分割事件のうち、8割近くが相続財産5,000万円以下、3割が1,000万以下というデータがあります。特に「不動産」は分割が難しく、トラブルの原因の一つになっていると考えられます。
家族間のトラブルを避けるには、生前の準備や、相続人が信頼できる相談先や依頼先を見つけることも大切です。
「遺言信託」「遺言代用信託」「終身保険」などの前もっての準備、認知症に備えて「民事信託に基づく預金口座」「後見制度支援預金」などのサービスを利用するのも一つの方法です。
相続の際のご家族の負担を軽減するため、専門家や専門機関への相談は大切ですが、そこでも留意する点があります。
司法書士、行政書士、土地家屋調査士などの個別の専門家に依頼をするとなると、専門家の元を訪ね、都度書類を揃えて提出することとなり、手間や時間がかかります。
それに対し、専門家と連携し一括対応をしてくれる専門機関に依頼できれば、手間も負担も少なくなりますので、その点も考慮しながら依頼先を選ぶとよいでしょう。
財産を遺す方法には、亡くなってから行われる「相続」と、亡くなる前に行う「生前贈与」とがあります。
税金を比べてみると、相続税に比べ生前贈与で支払う税金の方が多く見えますが、生前贈与には非課税枠が設けられているため、この仕組みをうまく利用して相続の準備をすることができます。ただし、不動産の贈与となると、課税負担が大きくなることもあるので注意が必要です。さらに、贈与税等の制度の見直しについて検討が進められているため、将来的に相続税や贈与税の内容が変更される可能性も。専門家の意見を参考に進めることをおすすめします。
図:一般贈与財産用(一般税率)
| 基礎削除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
| 基礎削除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm図:相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
七十七銀行では、「遺言信託」「遺言代用信託」「終身保険」など、生前の備えはもちろん、相続をワンストップでサポートできるサービスもご用意しています。
「自分の相続、心配だけどどこに何を相談したらいいのか・・・」、「親の相続、税金とか不安だな・・・」などのご心配がある方は一度身近な銀行に相談してみるのもよいかもしれません。
【七十七銀行 関連ページ】
七十七銀行のシニア向け商品・サービス
https://www.77bank.co.jp/sonaeru/shintakudairi/index.html【参考サイト】
知るぽると
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/sozoku_zoyozei/
※この記事は2022年4月現在の情報を基に作成しています。
今後変更されることもありますので、ご留意ください。